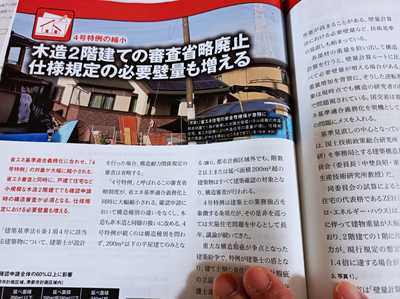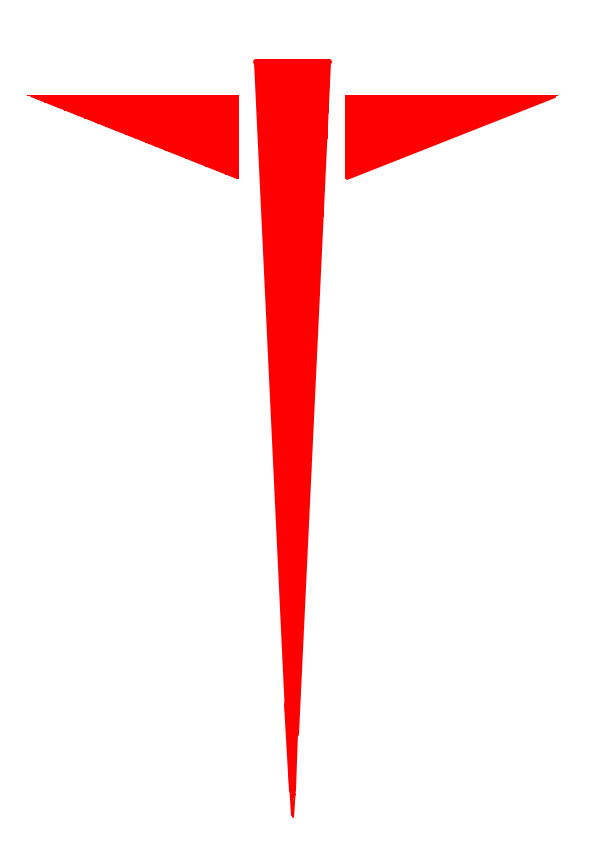2025年の建築基準法法改正にむけて ぼやき・・・ [住宅]
2025年の建築基準法法改正ですが、当事務所に構造設計依頼が増えているか? といえば まだ ですね。
なんか 感覚的ですが、業界的に「鈍感」?と感じてます。
というか そんなに仕事がないのかもしれません。
工務店の倒産も かなりある昨今。
仕事が減っっている とうのもあるし、家を建てる方も 物価高 給料もあまり伸びない 伸びても物価に追いつかない・・・で、 結局 ローンも組めない。
なので 家を建てない・・・ という具合ですね。
そもそも論ですが、新築の家を買う 持つ! は、ファイナンス的にはいい事じゃない と昨今 言われています。
賃貸が一番だとか言われてますが、当方がお勧めなのが 新築じゃなく 中古で家を買い それをリフォームですね。
日本には かなりの中古住宅があり その中古住宅は かの省エネ基準からも 大きく外れているものなんですが その中古住宅を解体処分する方が そもそも論 CO2がいっぱい出ると言えます。
今ある 中古住宅を何とかする方が 省エネじゃないか?とも 思う次第。
当方の住む 柏市周辺も空き家が多く、その空き家を 空き地にし その空き地を分割して 分譲住宅 というパターンも多々あり、相続した子世代は 都内のマンション住まい という具合なのだろう。
ファイナンス的には、物価の安い地方または都内の衛星都市に住み、 都内にはあまり行かず リモートで仕事し、住む家は 安い中古であれば、金銭的には かなり楽になる と思うんですがね。
(当方の仕事と相反する考えですがね・・・・)
それはさておき、2025の法改正に向けての動きが あまり活発に感じないかなあと。
あとで 泣きを見ないようにしてほしいものですね。
今年最初のブログでしたね・・・ [住宅]
昨年のお盆から なんと更新しておらず!!(笑)
いけませんね。
いけませんね。
今年も既に 1月も終わり、残り 330日ほど・・・
今年の後半から 建築基準法改正の影響が出始めるでしょう。
今年の後半から 建築基準法改正の影響が出始めるでしょう。
実は、我々の建築業界も 今現在、人手不足。
設計事務所をたたまれてしまう方もいらっしゃいます。
もっとも たたまれる人は、年配者の方ですが。
この法改正で 「もう やめる」という方も かなりいらしゃるかと思います。
今年 来年 と 日本経済も含め 建築業界も大波に見舞われそうですね。
意匠設計について 思う事 2023年お盆 [住宅]
当事務所は 一応 意匠設計もやっている。
といっても、ほとんど 構造設計の仕事が多い為、そんなにできない。
ペースも違うので、構造設計と意匠設計を 両方というのは 結構辛いことが 以前 やったため わかる。
とはいえ、意匠設計の仕事でも、確認申請出すとか あまり考えない部類の仕事だとなんとかなる。
意匠設計は 実は 考えている時間が多く、いわゆる働き方改革で 時間を区切られて 仕事できるかと言えば、多分 できないと自分は思っている。
住宅の計画については 答えがなく、アイディア勝負なのだ。
マンションの計画も 容積率から床面積を絞り出し あとはプラン という流れでやる分にはまだ 答えのない住宅の設計よりはましかなあと思うが、住宅はずっと考えていなければならない。
マンションの計画も 容積率から床面積を絞り出し あとはプラン という流れでやる分にはまだ 答えのない住宅の設計よりはましかなあと思うが、住宅はずっと考えていなければならない。
ふとしたことで アイディアが出たりとか その瞬間に 図面かかないと表現できないとか そういうのもあったりする。
構造はそうではなく 結構答えがはっきりしているので、作業に近い。
想像性 アイディアは、なかなか 構造モデル上 FIXできない時に必要だが それでもやることは限られている。なので、作業化しやすい。
だから 特別な仕事だとは 思う。意匠設計は。
しかしながら、相も変わらず 同じことを 経済評論家 藤巻健史風に何度もいう事となるが、やはり、構造上の知識や考え方がないので、特別な仕事であるのはもちろんだが、実際に成り立たたない場合もあり、構造の知識が不可欠と言えるが、現状は難しいだろう。
しかしながら、相も変わらず 同じことを 経済評論家 藤巻健史風に何度もいう事となるが、やはり、構造上の知識や考え方がないので、特別な仕事であるのはもちろんだが、実際に成り立たたない場合もあり、構造の知識が不可欠と言えるが、現状は難しいだろう。
国土交通省は、甘く見ていると思う。
一級建築士が どのくらいできているのかとか分かっているのだろうか??
2025年は、構造だけでなく 省エネも加わる。
ダブルで「できない」設計者も出てくるだろう。
省エネは テクニックはあるものの、基本的には 高断熱の窓を設置する事と、壁・屋根・床 断熱をどうするかということで だいたい決まる。
その他、気密工法といって 外気が入らないような 気密性能を上げる努力が必要となる。
気密については、多分、気密専門業者に頼むとか 自身でノウハウを現場監理で生かすかで なんとかできるかもしれない。気密は 性能指標を出して、この数値以上で作れ! と指定する場合もある。
この省エネがらみと構造は 関係ないのか? といえばそんなことはなく、屋根断熱の時に、構造では水平構面をどうするのかで 納まりも関係するし、外壁の耐力壁で 筋違を使用する場合も 断熱材の入りが悪い 等 マイナス面も出てくることもあり、その辺は 設計者の考えが必要となる。
話は元に戻るが、今 住宅設計者は、ただプランができればいいのではなく、構造や省エネに配慮した 実現できるプランを作る必要があり そういう設計者が必要だという事だ。
しかしながら 再三書いているが 現状では 不安だ。
プラン完成し、いざ契約し じゃあ 確認申請出します! という場目で 構造上成り立ちませんので プランやり直し ついには お施主が契約解除 もありえるなあと思っております。
4号特例縮小について 審査機関との世間話(展望) [住宅]
4号特例縮小について 2025年なので、あと2年切っている。
当然ながら、対策するには? 結局、骨抜きなのでは? と いろいろ話が出ているが、昨今の、税務関係のインボイスの件が参考となるだろう。
インボイスといえば、結局、中止・延期論はなく、進むことになった。インボイスについては、軽減策なども出て、当然ながら、税金が増える話なので、財務省としても進めたかったのだろう。このインボイスの様子が 4号特例縮小も同じ道をたどるのではと予想してます。
軽減策については、従来の壁量計算でなんとかする方法が出ているが、この方法というのが、現在の壁量計算で軽い屋根の1階の場合で比較すると 1.8倍となる壁量という案が出ている。(日経アーキテクチュア 2023.2-9号)これは、ZEH対応という事もあるようで、俗にいう、性能評価の1.5倍 よりも高く、許容応力度計算を考えると、このくらいあれば、計算した場合の1.5倍壁量に合致する量とも言えます。
しかしながら、この1.8倍は、現実的に受け入れがたく、壁倍率5.0倍MAXでの土俵で1.8倍は、壁だらけだろうと思われます。許容応力度計算の7倍MAXで、高倍率壁を使用する設計がベストとも言えますね。
さて、軽減策は置いておいても、結局 許容応力度計算 する ということになるのですが、意匠設計者さんたちにも または工務店さんたちも、計算ソフトがあればできる! と思われている方が多数いますね。
ここから今回のお題の審査機関との世間話 なんですが、私は 数社の審査機関の構造担当者と話をすることができました。この4号特例縮小については、審査機関にも重要な問題で、今まで、4号で済んだともいえる、2階建て木造住宅が 全て構造計算必須となるから当然だろう。
審査機関としては、申請料が値上がりできるメリットがあるが、審査に時間がかかるデメリットが出る。
この 審査に時間がかかる ということは、実は さきの計算ソフトがあれば解決できる とおもっている設計者たちがいるからなおさらのことだと思っている。
というのも、いわゆる計算ソフトで NGなく OK と出ているから 大丈夫なんだ。と「勘違い」している人が多発するからだ。
ソフト会社が講習会するにしても、分譲住宅の基本的なレベルでのモデルでの講習なので 少しでも変わる というか、プランごとに全て違う!とも言える内容なのに、正確にソフトに入力できるのか?がまずは 第一のハードル。自分が思うに、この件は、場数を踏んでいないと 対応は難しいと思う。しかも 年間10棟 程度だと、10件分の経験値がもらえるにしても、自分からしても そんなに多くない経験値だと思う。
もっとも 分譲住宅レベル程度の住宅がメインで設計している会社ならば 2年くらいである程度できると思います。いつも同じよう仕様の家ならば、パターンも同じだからだ。
しかし、そんな 計算書入力時点での不備は、いわゆる出直し案件で モデル設定から間違えている可能性もあり、審査機関は つっかえす案件が多発すると思っているようだ。
第二のハードルの話もしておくと、伏図である。
伏図には 審査に必要な事項 どちらかといえば 凡例 と その他 追記すべき事項を記入しなければならない。この記入すべき内容は 実は 審査機関によっても 微妙に違う場合も有り、いつも同じ審査機関で申請している会社ならば 多分 対応は難しくないだろうが、様々な審査機関とやり取りしている当方としては、この件は 「いつもこの審査機関」と決めて申請していれば、最初は苦労するだろうが、2年くらいすればなれるだろうと思う。
第三のハードルは、計算書と伏図以外の 添付の計算書や書類 である。
認定書のようなものは 出せば問題ないが、添付の計算書は 別途特別に検討する箇所が出てくる。例えば、深基礎 高基礎のような 大きな基礎の場合、土圧の検討としたのか? とか、人通口の検討(これは ソフトによっては 付いているものもある) 鉄骨階段を使用の場合は ササラ板等の検討 特殊形状の基礎ならば その検討 等である。これは、下手すると いつも違う検討を要求される。
ここは 2年経っても 慣れることはないだろう。
3つのハードルを書いたが、審査機関と4号特例縮小について話をすると、上記のような話となる。
特に第三のハードルは建物が変わった形態をしていると 別検討書が必要となってくるので、計算ソフトで全部してくれると思っている人であれば 対処不能と言える。
しかしながら、この計算ソフトに入力出来て 申請できる状態になったものの話で、そもそも 「成立しない」というのもある。多分だが そちらの方が多いのではと予想する。
特に 自分が意匠設計者とやりとりする中で、「行けますか?」という具合で、成立しているかも自分で判断できないのが現状だ。
意匠設計者のプラン・設計の時点で、成立しているかわからないということは、これは施主との契約破棄的な話にならないだろうかと心配している。
国土交通省は、建築士にそれなりの裁量権と知識知見が備わっていると思っているようだが、多分 かいかぶりしていると思う。
2025年は とんでもなく大混乱の年となるだろう。
収束するには、2年はかかるだろう。
やめてしまう設計者も多発するだろうし、当方のような低層木造をやっている設計者も大変な年になると予想している。
ログハウス(丸太組工法)の立ち位置 [住宅]
住宅等 低層木造住宅の構造設計を行っている当方。
軸組工法(いわゆる一般的な工法で 在来と言われてます) 2x4工法 丸太組 と大きく3つに大別してますが、当方は 現在、主に、軸組工法と丸太組のお仕事が多いです。2x4は時々 でしょうか。
これら3つの工法は 主に 軸組工法=日本古来の工法 2x4工法=主に北米の住宅の工法 丸太組=ヨーロッパや北米 がもともとの発祥で、丸太組は 日本では正倉院で使われた校倉造と言われた工法でもあります。
さて、軸組工法は最近は 耐震壁が必ずついてますので、壁で持たせる2x4工法とそんなに変わらなくなってきてます。軸組も2x4も 軸力は 柱 又は スタッド(壁の軸材)で基礎まで力を流します。梁の考えは どの工法もさほど変わりませんが、丸太組工法は、柱はなく、積んでいる丸太で基礎まで軸力を流しますが、軸力を流す点は、壁そのものが柱みたいなものなので、ある意味、丸太組工法はもっとも鉛直力に強いということになります。
丸太組同士は、「ダボ」と言われるつなぎ材 または 鉄筋(ボルトのうようなもの)で固定又はつなぎ、横ずれしないように固定します。
つまり、丸太組は 横ずれ=せん断力 を意識する工法なんです。
ですので、耐力壁の代わりに ダボの強さ/本数をチェックするのが 主なんです。
こうして書いている丸太組工法は、軸組工法とも2x4とも ぜんぜん違うと言えますが、困ったことに、その上に載る2階部分の設計が厄介で、ビルダーさんによって、2x4であったり 軸組であったりします。
確認申請において、構造計算を要求されることも多いのですが、2階の耐力壁をチェックしなさいと言われたとき、やり易いのが、2x4で、軸組は2階の壁が完全に立ち上がったものに近い場合は採用でいますが、やってて分かりますが、軸組は構造的に不向きと考えます。
というのも、よくある、小屋裏2階的丸太組 となった場合、屋根の始まるもっとも低い母屋が、仮に丸太組でなく、2x4壁で立ち上がった壁の上に載る母屋だとします。2階内部で耐震壁が取れないともなれば、この立ち上がった壁を評価しないといけないのですが、軸組だと 階高の1/2以上でないと耐力壁にならない という規定により、成立せず、耐力壁の高さ制限がない2x4であれば 成立する といったことがあり、明らかに2x4の方がやり易いということになります。
日本だと どうしても在来工法の方が 大工さんの手が見つかりやすく、2x4だとできないという大工さんも多いかと思います。
なので、2階は軸組 という選択をされる方も多いですが、場合場合で、使い分けるようにしないと、確認申請や中間検査で痛い目に会ってしまいそうですね。
4号特例縮小について 現段階での予想 2022年4月時点 [住宅]
建築基準法において、低層木造住宅等は、構造計算が不要な確認申請 すなわち 「4号特例」 というもので、不要となってますが、「不要」ではなく、意味的に言えば 設計する建築士が「やっている」想定の下 特例があると考えるべきで、もし、構造計算をしているはずなのに耐震的におかしい 耐震壁量が少ない とかで裁判を起こすと、構造計算していない場合 建築士が義務を果たしていない ということで 原告が必ず勝つ という事態となります。これは、日弁連も「違法」と言っており、「4号特例」はとんでもない抜け穴 と揶揄されています。
もっとも、4号特例は、そもそもなんで特例なのか?
それは、大工さんや工務店が いざ 構造計算しろ! というのに対応できないから が理由なのではないかと 筆者は考えます。しかし、実際は、それをいい方に解釈し なくてもOKだとか 軸組計算で問題ないと判断されてます。しかし 根本的には 最初に述べた通り、「建築士が構造計算やっている」とおう想定であり、軸組計算についてはかなりグレーです。
とはいえ、住宅性能表示においても、構造計算するルート以外に、簡易計算ルートもあり、軸組計算が法律的にダメとは言っていないのも確かで、「建築士が構造計算やっている」という想定は そこまで想定はしていない とも言えますね。ともかくもグレーだったわけです。
しかし、2025年改正に向け 今回、パブリックコメントが出て、4号特例を縮小したいなあ~ というニュアンスで国交省から出ました。
この件について、各設計者は意見がまちまちですが、「木造のほとんどが構造計算必要なんて勘弁してほしい」と考えている方も半数近くいらっしゃることでしょう。(実際の割合はわかりませんが)
様々な設計事務所とお付き合いしてる当方としても そんな設計者さんたちの様子や こうあるべき!という話は次回以降とし、今回は、展望を書いていこうかと思いますが、4号縮小としては、2025年にないのかあるのかといえば、「とりあえず ある だろう!」と考えます。
なぜならば、省エネ申請も 施主説明義務 というものができ、実質的に省エネ計算しないといけなくなりました。(実は構造も「伏図は保存義務のある書類」となり、設計事務所はプレカット図でもOKですが 保存しなくてはいけません。)この実質的に というのに意味があります。省エネ自体も 重量を増やす行為なので、今までの軸組計算では耐震性能が確保できない問題もあります。つまり、省エネしたら 耐震にならないという変な結果となります。
実は、全棟省エネ計算したいが、審査が追い付かないと 受け付ける確認審査機関から意見があったようです。つまり、その省エネ計算が間違っていようとも、とにかくやって書類を保存し 説明しろ ということです。
これは 構造についても同じとなると考えてます。現在の審査で 木造のほぼ全棟(だいたいの平屋は除かれますが)を確認申請時に構造審査は難しいと 自分も各審査機関の担当者にヒアリングしてみると そんな回答が得られました。審査費用が上がり、会社的には潤う面もあるが、数が増えすぎる・・・・ との事。
一方 我々 構造設計サイドも件数が増えすぎて対応できないと考えます。これは同じです。
しかし、なぜに結局縮小化と言えば、はやり法律的には 完全なグレーで 日弁連からも違法と言われている事をほっとけないし、何よりも 省エネによって 建物の重さが増えて、耐震性が落ちてしまっては意味がありません。
そう考えると、2025年の改正は、「4号特例縮小!」
実際には、「構造計算は義務化。審査はしなくても書類保存義務ができる!」
と考えます。その保存書類ですが、「構造計算書」が入る ということです。
これで、事実上の 4号縮小完成です。
たぶん そうなるだろうと 今は考えてます。
衝撃の2025年 4号特例縮小 [住宅]
当事務所は 特に影響なく むしろ歓迎とも言えますが、2025年度に建築基準法改正となり、
今まで 喉の奥に刺さった とげのような 「4号特例」が縮小されます。
縮小内容として、2階建の低層木造住宅 平屋も200㎡以上 は 「構造計算必要」となります。
今回、そうなった理由は、省エネ法により 断熱材や 太陽光パネルを載せると 現在の仕様規定では 構造耐力が足りない ということで、もともとその危険性は 当方も指摘していたことです。
ゆえに、今回、そのようなへんこうとなってますが、いままで不要で作ってきた 意匠事務所や工務店には寝耳に水ですね。
大工さんレベルではもはや どうにもならない話となってしまいます。
当方も仕事が増えるとは考えてますが、それ以上に 何も構造的な事を考えず作ってきた人たちが 突然できるようになるのかは できるわけなく、結局、仕事も難しくなるという印象です。
本当にエコなのか? 太陽光パネルなどの省エネ設備 [住宅]
環境省が 太陽光パネルをこれから 年間新築の家の 6割に載せるよう 方針・・・・ とありましたが、そもそも 本当に 環境に良いのか エコなのか??
太陽光パネルは ちょっと前まで、電力会社が買い取って それで載せる お得感を演出していたが、今は、買取は消極的で、だんだん値段も下がり、当初、収支的な書類で太陽光を載せると判断したお施主さんには 許容できない結果となっている。ある意味 だまされている。
自分は 太陽光パネルについては、そもそも電力会社の買取がずっと続くとは思っていなかったし、そもそもエコなのか? と思っていました。
太陽光パネルは調べると、15年前に比べ 価格も下がりましたが(今は 逆に上がりましたが)、原料とパネルを作る人手も 実は 昨今、人権問題で噂の ウイグル等で作っている模様で、パネルの材料は山を切り開き 鉱山のように自然破壊して 原材料のシリコンを採取しているようです。人件費を安く抑えたい ということでウイグルで作るんでしょうが、人権問題がかかわっているので、もはや 自然破壊と人権侵害で ダブルで 大問題なもとのなってます。この話を聞くと 一体何が エコなのか・・・・です。
カーボンニュートラル とか カーボン~ と二酸化炭素を抑えると言ってますが、抑える機械設備を作るのに二酸化炭素を出している現状で、エコはただの売り文句となってます。こういうことって多く、SDGsも 自分から見ると 売り文句に感じます。
太陽光パネルは 当然ながら 載せると重くなり、既存の家に載せると 耐震性が下がります。地震力は、建物の重さが基で、発生します。つまり、軽ければ 地震では揺れないのです。でも、なぜか載せることを推奨してますね。新築であれば、最初から載せることを前提で設計すれば 当然 耐えられる建物となりますが、当然 多少なりとも 本体のコストアップにつながります。
太陽光パネルを載せるよりも 耐震性能を向上することが 国家安泰と 被災後の復旧 そして 被災後の見舞金等を減らすこともでき、日本の様な災害大国では そっちが先だろうと 自分は思うのですが・・・
そういえば、太陽光パネルは 後載せにしても 最初から載せるにしても、屋根と別ならば、屋根が塗り替え・修理 という場合は いちいち取り外さないといけません。瓦と一体型もあるので、それであれば その心配もないのかもしれませんが、板金屋根となると 15年程度で 塗り替え必要となったりします。その場合 どうするのでしょうか・・・
いづれにしても、太陽光パネルは 載せていいものなのか・・・・ エコだとか 儲かるとか 得だとか そういう目線で考えるだけではいけないのではないかと思います。
意匠設計と構造設計の両立! [住宅]
普段、構造設計がほぼ専業化している当事務所が イレギュラーなんでしょうが、意匠設計と構造設計の併進は、ペースも違うので結構大変・・・ 意匠は施主直接に対して、構造は意匠設計者。構造はしばらくすると審査機関からの質疑・・と次から次。
自分の意匠設計は、実は構造ができる最大の武器を利用した、構造検討しながらの 意匠設計。普通の設計事務所は、というか 大概の事務所はできない。仮に構造のソフトを使っていても、圧倒的構造設計の場数が少ない為、判断力・設計力に差がある。要するに ソフト持っていても知らない人は設計できない。
というわけで 自分はできるので、梁の大きさ 耐震性等も 逐次調べながら進めるわけだけど、結構大変ですね。
とはいえ、手戻りもなく 安心な設計ができる。
木造主体の設計者とRC・鉄骨系の設計者の違い [住宅]
久々の更新です。というか コロナ禍ですが 全然暇ではありません。
むしろ 忙しく、今年に限っては 久々の意匠のお仕事も入り 多忙を極めております。
意匠と構造の仕事は ペースが異なり、やはり一緒にやるとなると結構大変です。その話は おいおい~
さて、木造主体の設計者とRC・鉄骨系の設計者の違いは、はっきり言えば「寸法感」でしょう。
RCや鉄骨は あまり材料の規格に左右されません。もっとも、本当はあるのですが、外壁に貼るタイルだったりALCコンクリート壁であったりと、ないわけではないんですが、現場サイドが えいやあ とやっている感じで、設計者はおまかせ感覚かと思います。
細かく言えば、木造は全て 900とか910 とかの いわゆる尺で縛られていることが多く、木造を最初から始めた人は寸法感が尺で取られていることが多いです。しかし、人間の寸法感があるというのは 実際の家でも 「このくらい」というのが分かりやすく 完成時 あまり失敗はないのかな と思います。
逆に 鉄骨やRCを主に設計している設計者は、尺の寸法感がなく、メートルだったり、はたまた 1.2mのような数字を割っていたりと、いろいろありますね。
自分は様々な意匠設計者の図面を見ているので、感じられますが、意匠設計者同士 他人の図面を見たりするのはあまりないので、教わった先生や先輩の癖がそのまま移ることが多く、系統は そのまま残る感じです。
自分が思うに、木造は やはり「尺」で書いた方がよく、現場にも伝わりやすく、また、材料の無駄も少なく、ミスも少ないと感じます。
過去、それを設計者に失礼ながら指摘したら、「もうあなたには頼まない」と言われたことがあります。
でも、その意匠設計者は、他でも 特に現場では いろいろ言われているとは思うので、自分だけではないかと思うんですがね・・・・
設計者を選ぶにも 普段 構造は 木造? RC? 鉄骨? と聞いてみたらかがでしょうか???
追記
昨年 つてがあって「コノイエ」という解体系の会社さんの建築家紹介サイトに掲載されました。
昨年 つてがあって「コノイエ」という解体系の会社さんの建築家紹介サイトに掲載されました。
そこでは 意匠設計者を結構 ぼろくそ言ってます(笑) 参考にしてください。(笑)