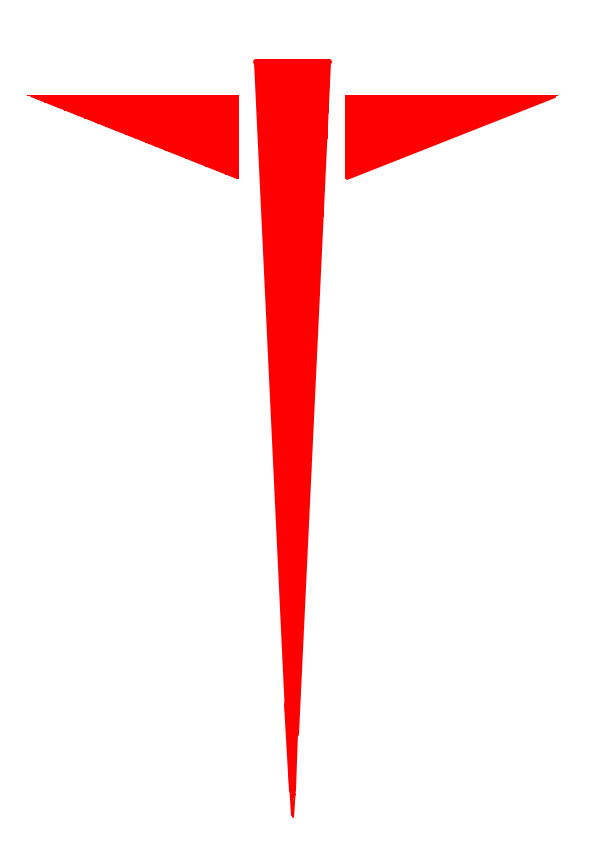前の3件 | -
2025年の建築基準法法改正にむけて ぼやき・・・ [住宅]
2025年の建築基準法法改正ですが、当事務所に構造設計依頼が増えているか? といえば まだ ですね。
なんか 感覚的ですが、業界的に「鈍感」?と感じてます。
というか そんなに仕事がないのかもしれません。
工務店の倒産も かなりある昨今。
仕事が減っっている とうのもあるし、家を建てる方も 物価高 給料もあまり伸びない 伸びても物価に追いつかない・・・で、 結局 ローンも組めない。
なので 家を建てない・・・ という具合ですね。
そもそも論ですが、新築の家を買う 持つ! は、ファイナンス的にはいい事じゃない と昨今 言われています。
賃貸が一番だとか言われてますが、当方がお勧めなのが 新築じゃなく 中古で家を買い それをリフォームですね。
日本には かなりの中古住宅があり その中古住宅は かの省エネ基準からも 大きく外れているものなんですが その中古住宅を解体処分する方が そもそも論 CO2がいっぱい出ると言えます。
今ある 中古住宅を何とかする方が 省エネじゃないか?とも 思う次第。
当方の住む 柏市周辺も空き家が多く、その空き家を 空き地にし その空き地を分割して 分譲住宅 というパターンも多々あり、相続した子世代は 都内のマンション住まい という具合なのだろう。
ファイナンス的には、物価の安い地方または都内の衛星都市に住み、 都内にはあまり行かず リモートで仕事し、住む家は 安い中古であれば、金銭的には かなり楽になる と思うんですがね。
(当方の仕事と相反する考えですがね・・・・)
それはさておき、2025の法改正に向けての動きが あまり活発に感じないかなあと。
あとで 泣きを見ないようにしてほしいものですね。
今年最初のブログでしたね・・・ [住宅]
昨年のお盆から なんと更新しておらず!!(笑)
いけませんね。
いけませんね。
今年も既に 1月も終わり、残り 330日ほど・・・
今年の後半から 建築基準法改正の影響が出始めるでしょう。
今年の後半から 建築基準法改正の影響が出始めるでしょう。
実は、我々の建築業界も 今現在、人手不足。
設計事務所をたたまれてしまう方もいらっしゃいます。
もっとも たたまれる人は、年配者の方ですが。
この法改正で 「もう やめる」という方も かなりいらしゃるかと思います。
今年 来年 と 日本経済も含め 建築業界も大波に見舞われそうですね。
意匠設計について 思う事 2023年お盆 [住宅]
当事務所は 一応 意匠設計もやっている。
といっても、ほとんど 構造設計の仕事が多い為、そんなにできない。
ペースも違うので、構造設計と意匠設計を 両方というのは 結構辛いことが 以前 やったため わかる。
とはいえ、意匠設計の仕事でも、確認申請出すとか あまり考えない部類の仕事だとなんとかなる。
意匠設計は 実は 考えている時間が多く、いわゆる働き方改革で 時間を区切られて 仕事できるかと言えば、多分 できないと自分は思っている。
住宅の計画については 答えがなく、アイディア勝負なのだ。
マンションの計画も 容積率から床面積を絞り出し あとはプラン という流れでやる分にはまだ 答えのない住宅の設計よりはましかなあと思うが、住宅はずっと考えていなければならない。
マンションの計画も 容積率から床面積を絞り出し あとはプラン という流れでやる分にはまだ 答えのない住宅の設計よりはましかなあと思うが、住宅はずっと考えていなければならない。
ふとしたことで アイディアが出たりとか その瞬間に 図面かかないと表現できないとか そういうのもあったりする。
構造はそうではなく 結構答えがはっきりしているので、作業に近い。
想像性 アイディアは、なかなか 構造モデル上 FIXできない時に必要だが それでもやることは限られている。なので、作業化しやすい。
だから 特別な仕事だとは 思う。意匠設計は。
しかしながら、相も変わらず 同じことを 経済評論家 藤巻健史風に何度もいう事となるが、やはり、構造上の知識や考え方がないので、特別な仕事であるのはもちろんだが、実際に成り立たたない場合もあり、構造の知識が不可欠と言えるが、現状は難しいだろう。
しかしながら、相も変わらず 同じことを 経済評論家 藤巻健史風に何度もいう事となるが、やはり、構造上の知識や考え方がないので、特別な仕事であるのはもちろんだが、実際に成り立たたない場合もあり、構造の知識が不可欠と言えるが、現状は難しいだろう。
国土交通省は、甘く見ていると思う。
一級建築士が どのくらいできているのかとか分かっているのだろうか??
2025年は、構造だけでなく 省エネも加わる。
ダブルで「できない」設計者も出てくるだろう。
省エネは テクニックはあるものの、基本的には 高断熱の窓を設置する事と、壁・屋根・床 断熱をどうするかということで だいたい決まる。
その他、気密工法といって 外気が入らないような 気密性能を上げる努力が必要となる。
気密については、多分、気密専門業者に頼むとか 自身でノウハウを現場監理で生かすかで なんとかできるかもしれない。気密は 性能指標を出して、この数値以上で作れ! と指定する場合もある。
この省エネがらみと構造は 関係ないのか? といえばそんなことはなく、屋根断熱の時に、構造では水平構面をどうするのかで 納まりも関係するし、外壁の耐力壁で 筋違を使用する場合も 断熱材の入りが悪い 等 マイナス面も出てくることもあり、その辺は 設計者の考えが必要となる。
話は元に戻るが、今 住宅設計者は、ただプランができればいいのではなく、構造や省エネに配慮した 実現できるプランを作る必要があり そういう設計者が必要だという事だ。
しかしながら 再三書いているが 現状では 不安だ。
プラン完成し、いざ契約し じゃあ 確認申請出します! という場目で 構造上成り立ちませんので プランやり直し ついには お施主が契約解除 もありえるなあと思っております。
前の3件 | -